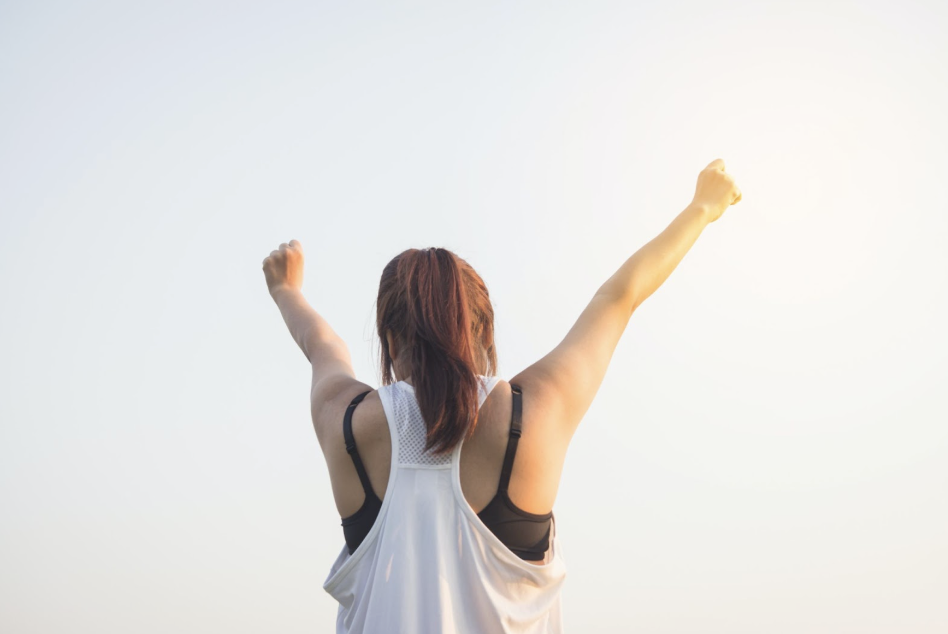毎年7月に入ると話題になるのが「土用の丑の日」。
夏の暑さで疲れた体にウナギを食べてスタミナをつけるという、古くから伝わる日本の習慣があります。
土用とは、立春、立夏、立秋、立冬の直前約18日間の期間を指し、その中で干支が「丑」に当たる日を「土用の丑の日」と呼びます。江戸時代、夏場に売れにくかったウナギを広めるため、学者・平賀源内が「本日、丑の日と書けば売れる」と提案したのが始まりとされています。
現代でもこの時期は、暑さで体調を崩しやすい季節。
そこで今回は、夏バテの症状・原因・予防・対処法までを解説していきます。
夏バテってどんな状態?

夏バテとは、高温多湿な環境下で起こりやすい体調不良の総称です。医学的な病名ではありませんが、日常生活に支障をきたすことも少なくありません。
代表的な症状:
- 体がだるい・疲れがとれない
- 食欲がわかない
- 胃腸の調子が悪い(下痢や便秘)
- 頭がぼーっとする・集中力が落ちる
- 眠りが浅く、疲れが抜けない
夏バテの主な原因とは?
夏バテの原因は一つではありません。主に以下の4つが挙げられます。
① 寒暖差ストレスによる自律神経の乱れ
屋外と室内の温度差によって自律神経が乱れ、疲れやすくなります。
② 水分・ミネラル不足
汗で水分と一緒に塩分やミネラルも排出され、軽い脱水状態に。これが体力低下の一因に。
③ 冷たい飲食物のとりすぎ
冷たいアイスやドリンクで胃腸が冷え、消化機能が低下。それが食欲不振につながります。食欲が落ちると、エネルギー不足やビタミン・ミネラルの欠乏が起こることも。
④ 睡眠の質の低下
寝苦しい夜が続くことで眠りが浅くなり、疲れが蓄積しやすくなります。
夏バテを防ぐ生活習慣・食事の工夫
夏バテを予防するためには、「体を冷やしすぎない」「こまめに水分補給をする」「しっかり食べてしっかり休む」ことが大切です。

◎生活習慣のポイント
- 冷房は「28℃前後」「風が直接当たらない位置」に設定
- 日中の外出時は帽子や日傘を活用し、体温の上昇を防ぐ
- 十分な睡眠を確保し、就寝1時間前にはスマホを控える
◎食事のポイント
- 3食しっかりとる(特に朝食を抜かない)
- そうめんなどさっぱり系+タンパク質・野菜の組み合わせ
- 発酵食品やビタミンB群、クエン酸を含む食材(梅干し、酢の物、豚肉など)を積極的に
夏の食卓に、からだにやさしい一品を。
「夏バテ=スタミナ食」と考えて、脂っこい料理に走るのは逆効果なことも。
そこでおすすめなのが、発酵調味料を使ったやさしい味付けの一品です。
例:
- ウナギを塩麹に軽く漬けて焼くことで、うま味が増して柔らかく。
- 甘酒をタレに使えば、砂糖に頼らず自然な甘さとコクがプラスされます。
自然な甘みやうま味が引き立ち、体にもこころにもやさしい味わいに仕上がります。
夏バテになってしまったときの対処法
それでも体調を崩してしまったら、以下のポイントを意識して生活を整えていくことが大切です。
- 水分と電解質の補給を意識する。
スポーツドリンクやハトムギ茶、味噌汁や・甘酒などで電解質を補いましょう。 - 消化にやさしい食事
おかゆや豆腐、うどんや温かいスープなどがオススメです。 - ゆっくりぬるめのお風呂に浸かる
38~40℃のお湯にゆっくり浸かることで、自律神経が整いやすくなります。 - 無理な外出や運動を控える
炎天下の外出や激しい運動は控え、体力回復に努めましょう。睡眠の質にもこだわる場合はクーラーや寝具の見直しも。
無理に食べる・動くのではなく、できることから毎日の習慣に気を配ることが大切です。
最後に
夏バテは誰にでも起こりうる季節の不調。
大切なのは、「気づいたときにしっかりケア」することです。
welalaでは、夏を心地よく過ごすための発酵食品・ハーブティー・甘酒などを豊富に取り揃えています。
暑い日も、ほっとできる時間を食卓から取り入れてみませんか?
【welala公式HP】
【welala公式Instagram】